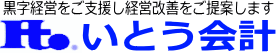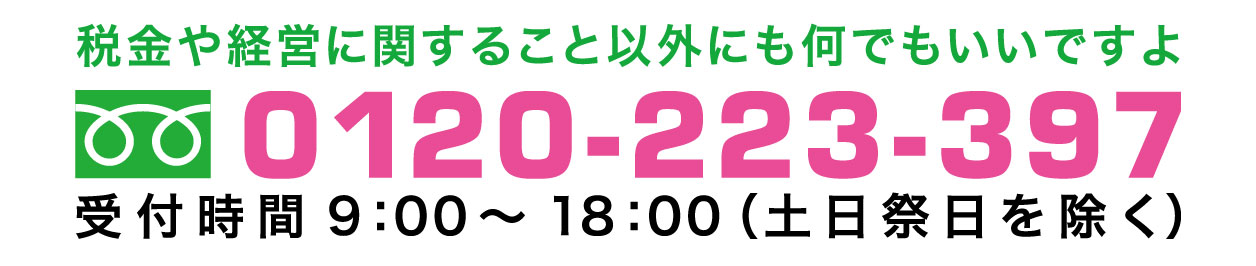相続対策
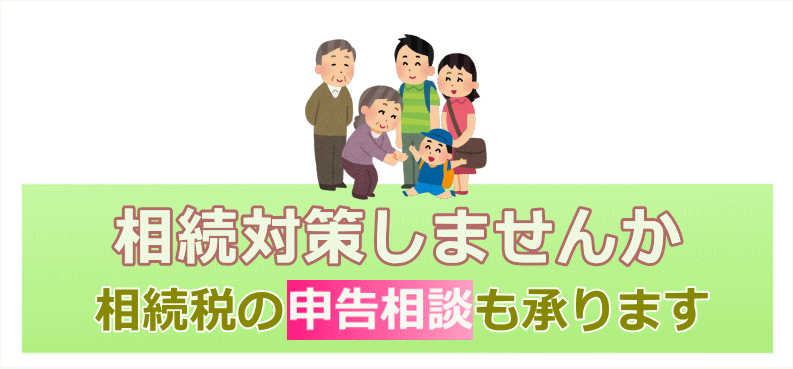
生前贈与として次のような方法があります
■ 暦年課税贈与(一年間あたり110万円まで非課税)
■ 相続時精算課税」制度の活用(2,500万円まで)
■ 贈与税の配偶者控除(婚姻期間が20年以上経過した方)
■ 子への住宅取得資金の贈与(父母や祖父母から20才以上の人へ、3,000万円まで)
■ 子や孫への教育資金の贈与(1,500万円まで非課税、30才未満)
■ 子や孫への結婚(300万円まで)・子育て資金(1,000万円まで)の贈与(20才から49才まで)
なお、遺言や養子縁組、借入による賃貸物件の建築など生前贈与以外の方法もありますので、お問い合わせ下さい。相談は初回の60分まで無料ですよ!
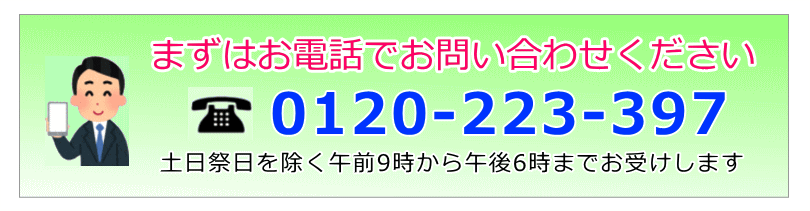
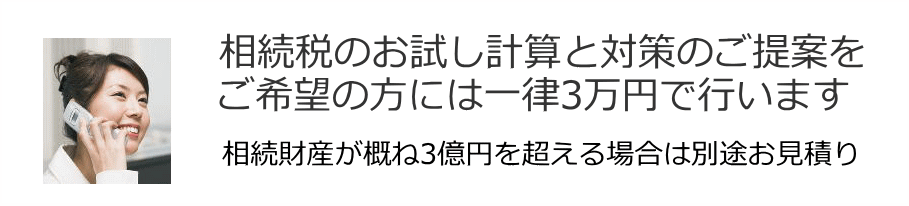
相続税の申告対象者が飛躍的に増加しています
東京国税局管内での申告割合はかつて約7%でしたが、平成27年改正以降は都内平均で約20%(つまり、亡くなられた人約5人に1人の割合でその相続人について相続税が課税)になったと云われております。
なので、合理的に考え対策を講じることで相続税額を少しでも安くできることがあるなら、今のウチにやっておくべきですね。そのために、ぜひ、相続税の試算をお勧めします。
私の体験からすると、申告をしなくてはならないケ-スと、しなくてもよいケ-スとの境目となる場合が非常に多いのです。
ぜひ一度計算をやってみて、安心したり相続対策を考えたりしませんか。
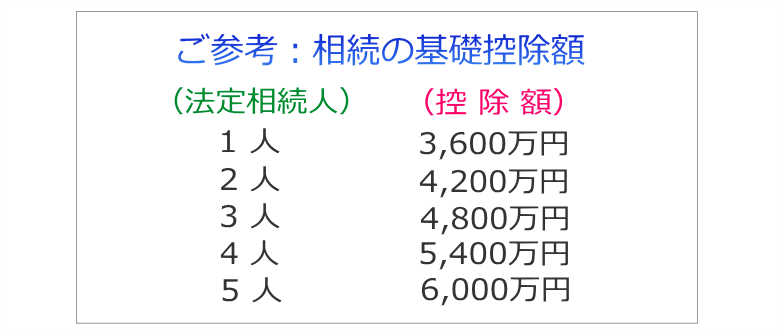
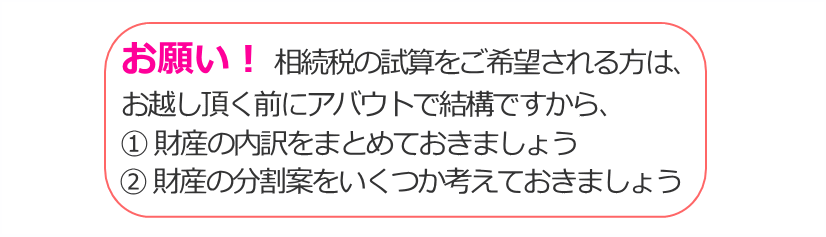 説明がし易くなるからです
説明がし易くなるからです
相続を絶対に争族にしないようにしましょう
誰も好きこのんで財産をめぐっていがみ合いをする訳ではありません。でも、結果的に、そのような事態に陥ってしまうのです。
何故でしょう? おそらく、皆さんの権利意識の高まりや、スマホの普及によりネットでいつでも調べることができることがそうさせるのだと思われます。「遺留分」がその典型的な例ですね。
そこで、ご両親としては、また、子供さんたちも、ご両親が元気なウチに争族にならない対策を立てることが賢明ではないでしょうか。
前もって両親の財産を計算して、今、万が一のことがあったらどれ位の相続税がかかるのか、或いは、相続税がかからなくとも、親や子供さんたちが納得できるように財産分けするにはどのようにしたら良いか、その判断基準を知っておく必要があります。
(ご参考) 2019年7月に施行された新民法では、遺留分は金銭債権の扱いになります。 このことにより、お金ですっきり解決することが可能になり、いわゆる「争続」が起きにくゝなったと云われていますが、事は単純ではありません。
なお、金銭の支払いに代えて不動産を渡す場合は譲渡所得として扱われ、譲渡益が発生するときは(譲渡)所得税が課税されますのでご注意。
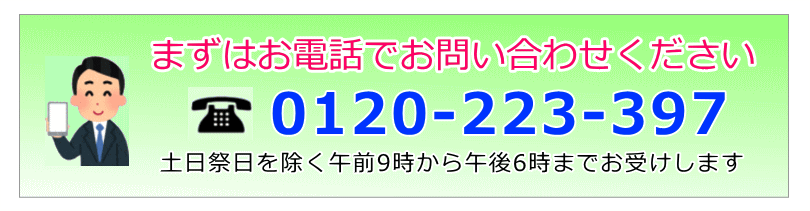
★ 東京駅から27分、新宿駅から21分